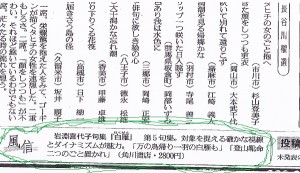俳 誌 探 訪 筆者大塚隆右
「ににん」2012年冬号より
ほとぼりのやうに残りし冬の菊 岩淵喜代子
「ににん」の代表である岩淵喜代子氏の作。歳時記の既述では冬菊と言えば、冬になっても残っている菊と、冬に咲く菊の二通りがあるようだが、ここはやはり前者であろう。なんと言っても「ほとぼり」という言葉遣いに惹かれた。花盛りの頃の印象が、いまなお余熱のように続いているさまを言っているのだが、措辞の巧みさに感心させられる句である。
燈火親し命ながらへ栗を食む 西田もとつぐ
病が小康を得たころの句であろうか。燈火親しむといえば読書や音楽鑑賞などのイメージがあるが、作者は重い病の後とあって、まだそのようなゆとりの境地には至らないまでも、栗を食べてみようかという気持ちになれるところまでたどり着いた。控えめな表現であればこそ、安堵感や喜びというものが充分伝わってくる。
打ち上げ大花火飽きる間もなく上がりけり 及川 希子
打ち上が花火の種類というのも無数にあるわけではなく、幾通りかが交互に現れる仕組みになっている。とすればしばらく見ているうちに飽きがくるのでは、と思われるのだが、尺玉の大きなものが次々に打ち上げられ、大音響とともに作裂する迫力を楽しんでいると、時間のたつのを忘れてしまうようだという、臨場感が伝わってくる。
ストーブのとろ火に溶けて眠る午後 木佐 梨乃
とろ火と聞けば即座に料理で使われるが、とろ火で三十分と煮込む、などの言葉が思い付されるが、ストーブに程よく暖められた部屋で、午後のひと時うつらうつらとまどろんでいる時の、なんともいえない心地よさを、自身がとろ火に溶けているようだと表現する、厨俳句ではないものの、男には及びもつかない発想の句である。
火祭りのあとの鞍馬の星の数 武井 伸子
昔から映画の時代劇などで鞍馬の火祭は、日本人にとってなじみの深い名前ではなかろうか。ここで作者は主役の火祭りには触れず、宴のあととも言える祭りのあとの闇の深さと、それゆえに一層際立つ無数の星の輝きのことを言っている。あかあかと燃え盛る炎の残像があってこその、星のまたたきの神秘さが、あざやかな対比として提示されている。
背なの子のいつしか眠る遠花火 宮本 郁江
飽きる間もない大花火と異なにり、ここでは遠花火である。高い階のマンションの部屋から見ていると、夏場の土日には遠くの花火がよく見える。おおむね間隔が長く音も聞こえないことが多い。作者もそのような花火を背中の子と一緒に見ていたが、とうとう眠ってしまったようだ。子供にとってはあまり刺激的でない遠花火の静かさ、間遠さをうまく表した句である。
賤ケ岳鴨の陣敷く余呉の湖 宇陀 草子
日本人にとって賎ヶ岳の名は、やはり秀占と柴田勝家の合戦や、いわゆる七本槍の逸話を伴って記憶されている。とすれば余呉の湖で鴨たちが、勝手に群れをなして泳いでいる様子を見ても、なにやら陣形を敷いての子細ありげな行動のように見えてしまう。想像力の働いた諧謔昧にあふれる句とかっている。